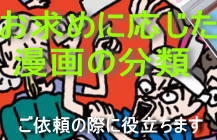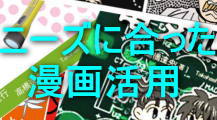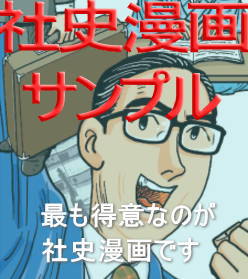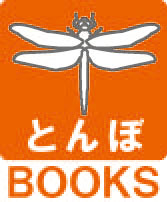�Ƃ�ڃX�^�W�I�́u����v�ɓ��������v���̖���Ƃ����̖��搧�쎖�����ł��B
�o�ŕs������̒E�o
| HOME�� ����Ƃ̃A�h�o�C�X�ƈ��S�T�|�[�g | |
|
�o�ŕs������̒E�o |
|
| �ڎ� | |
| 1.���������C���̏o�ŎЂ̎���͋ꂵ�� �@1-1.���Ă̏o�ŋƊE �@1-2.55�N�O�̐����ɉ�A 2.�d�q���̔g �@2-1.�d�q�o�ł̐L�� �@2-2.���̋Ɛтɍv�����閟�� 3.�d�q�R�~�b�N�̐��� �@3-1.�R�~�b�N���̏k���Ɠd�q�R�~�b�N�̐��� �@3-2.�R�~�b�N�ւ̈ˑ� 4.�掟�X�⏑�X�Ƃ̕t�������̕ω� �@4-1.�s��\���̕ω� �@4-2.���[���̊J�����O�ʈ�̂�ς��� 5. �o�ŋƊE�̕����� �@5-1.���ɍS��Ȃ��o�ŋ� �@5-2.�f�W�^�����Ɨ��ʂ̐��� |
|
| ���������C���̏o�ŎЂ̎���͋ꂵ�� | |
| ���Ă̏o�ŋƊE ���݂̎G���̔̔�������55�N�O�̐����������ł��B���{�����̒��������o�ϕ����𐋂��A���x�o�ϐ���������������Ƃ��邻�̎��Ɠ����Ƃ������Ƃł��B�������A�Ђ�����ł���A������͎Ηz���������̎p�ƍl���ėǂ��ł��傤�B �G���Ƃ����͍̂L�����t���č̎Z������悤�ɍ����̂ł��B�܂�A��Ƃ̃o�b�N�A�b�v������A�G�����̂��̂�����Ȃ��Ă��o�ŎЂƂ��Ă̓y�C�ł���Ƃ����Z�i�ł��B �悤����ɁA�L���͌i�C���ǂ����v�̂����Ƃ��S������킯�ł�����A���x�������ɂ͍L����t���ĎG�����o�b�N�A�b�v������Ɛ��Ȋ�Ƃ���������o�Ă����ƍl���Ă悢�킯�ł��B���̍D�i�C�������č��x�o�ϐ��������������̂����Ă̓��{�o�ςł����B �ł�����A�����͊�Ƃ̌i�C���ǂ��G�����ǂ�ǂ�o�ł���A��Ƃ��o�ŎЂ��傢�ɖׂ��������ゾ�����̂ł��B 55�N�O�̐����ɉ�A �Ƃ��낪�A�����̌i�C�͒���𑱂��A55�N�O�̒ᐅ���ɖ߂����̂ł��B�Ƃ��Ɋ������S�̏o�ŎЂ͋ꂵ��ł��܂��B�����␏�M�ȂǁA�����̖{�͔���܂���o�ŎЂ����f���̏�Ԃł��B�������A���������o�ŋƊE�ɂ����Ă��P�킵�Ă���̂��R�~�b�N�ł��B���悾���͊撣���Ă���̂ł��B |
|
| �d�q���̔g | |
| �d�q�o�ł̐L�� �o�ʼnȊw�������̒��ׂɂ��ƁA���ЂƎG���̓}�C�i�X�ł��d�q�o�ł̐L�т������đS�̂������グ�Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�܂��A���o�ŎЂR�Ђ̋Ɛт́A�����葱���Ă����L������グ���v���X�ɔ��]���A�f�W�^���ƍL���̑����Ŋe�Ђ��������v�ƂȂ��������ł��B �G���͓��{�̏o�ŗ��ʂ��x���Ă��܂����B���̎G����96�N���s�[�N�ɋ}���ɏk�����Ă��܂����B�����āA���̏k�����o�ŋƊE�̒�����������ɕ\���Ă���̂ł��B ���̋Ɛтɍv�����閟�� �������A���o�ŎЂ͋Ɛт]���܂����B���̔w�i�ɂ���͖̂���ł����B���̃R�~�b�N�͌��������̂ł����A�f�W�^���R�~�b�N���傫�ȐL�т������A����Ɋ����n�̓d�q���Ђ����v�ł����B���Ȃ݂ɁA�R�~�b�N�͓d�q����������܂����B |
|
| �d�q�R�~�b�N�̐��� | |
| �R�~�b�N���̏k���Ɠd�q�R�~�b�N�̐��� �d�q�R�~�b�N�̐����͑����Ă��܂��B�������A�R�~�b�N���͐��ނ��Ă��܂��B�R�~�b�N�S�̂Ō���u�����v�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�܂�A���̏k�����f�W�^���ŕ⑫���邱�Ƃɂ���Đ������ۂĂĂ���Ƃ������Ƃł��B ���������f�W�^�����������鐬���͓��ʑ������̂ƍl���܂��B���R�Ђ̋Ɛт��A�R�~�b�N���̗������݂�d�q�R�~�b�N���J�o�[���Ă����Ԃł��B�悤����ɁA�o�ŎЂ����v���グ�悤�Ǝv������d�q�R�~�b�N����ɐi�o����Ηǂ��Ƃ������Ƃł��B �R�~�b�N�ւ̈ˑ� �������A�����̏o�ŎЂ�������������������A�d�q�R�~�b�N�̎��v�p�C�͂��قǕω����Ȃ��ł��傤���炻��Ȃ�ɋ�킷�邱�Ƃ͕K��ł��B��������A�ǂ����Ă����R�Ђ����҂ɂȂ�Ƃ����킯�ŁA���ꂪ�킩���Ă��邩�璆���̏o�ŎЂ͑ǂ��Ȃ��B����ȂƂ���ł��傤���B �����A�d�q�R�~�b�N���������ێ����A���ꂩ��̏o�ŋƊE����������ł��낤���Ƃ͗\���ł��܂��B �o�ϐ������ɏo�ŋƊE�����C�Â����̂�����ł������A���������s��������E�o����̂�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B |
|
| �掟�X�⏑�X�Ƃ̕t�������̕ω� | |
| �s��\���̕ω� �{�̗����ɑ傫����^���Ă����̂��u�掟�X�v�̑��݂ł��B�o�ŋƊE�ł́u�o�ŎЁv�u�掟�X�v�u���X�v���O�ʈ�̂ƌĂ�ł��܂����B�o�ŎЂ��{�����掟�X�𒆌p���đS���e���̏��X�ɖ{����ׂ܂��B�������Ď������͖{�̔������Ƃ��ł��Ă����̂ł��B �������A�A�}�]���Ȃǂ̓o��ł��������d�g�݂��ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B����܂ł͏o�ŎЂƎ掟�X�A���X�����v����肭���z���Ă��܂������A�s��\���ɕω������܂ꂽ�̂ł��B�o�ŎЂ��璼�ڏ���҂ɖ{���͂����邱�Ƃ��e�ՂɂȂ�A����ɓd�q���Љ��������ƂŎ��̖{�����݂��Ȃ��Ȃ�f�[�^�������ǎ҂ɓ͂�����悤�ɂȂ�܂����B ���[���̊J�����O�ʈ�̂�ς��� ����ɁA�������[���̊J���ɂ���āA�������̓p�\�R����X�}�z�Ȃǂŗl�X�ȏ���e�Ղɓ��肷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�����������ɐڂ��鎞�Ԃ������Ȃ邱�ƂŊ������ꂪ���i����A�܂��܂��{�ɐڂ��鎞�Ԃ����Ȃ��Ȃ����̂ł��B ���������v�����d�Ȃ��āA���̖{�̕������ϗe���Ă��܂����B�S�����瑽���̏��X���p�������A�{�̎掟�X���ω������߂��Ă��܂��B |
|
| �o�ŋƊE�̕����� | |
| ���ɍS��Ȃ��o�ŋ� ����炩�̏o�ŋƂ͎��̖{�ɍS��Ȃ����Ƃ��ЂƂ̃L�[���[�h�ɂȂ�ł��傤�B�u���v����������u�o�Łv�Ȃ̂Ɏ��ɍS��Ȃ����ƂŊ��H�����o���̂ł��B �Ƃ��ɓd�q���ЂƖ�������Ɋ��p���邱�Ƃł��傤�B�R�~�b�N���������ƂōL�������Ɍq���邱�Ƃ��ł��܂��B�H�v����ŗ��v�͊m�ۂł���͂��ł��B �f�W�^�����Ɨ��ʂ̐��� �f�W�^���͎��̈����{�ɗv�����p���啝�ɍ팸�ł���̂ŁA�R�X�^�p�t�H�[�}���X�ɔ��ɒ����Ă��܂��B����o����Ȃ���Γd�q���Ђ������Œł���킯�ł�����A���Ƃ͗��ʂ�@���ɐ������邩�̖�肾���ł��傤�B |
|
| �Q�l�y�[�W�� �@�ŋ߂̖��掖�� �@����Əo�ŋƊE�̍��� �@�o�ŕs������̒E�o �@ �@�Ƃ�ڃX�^�W�I�̖��搧��� �@�Ƃ�ڃX�^�W�I�̐���t����� �@��� �@�Ўj���搧��̃����b�g �@�����̖ڈ� �@���搧��̏��i�Љ� |
|
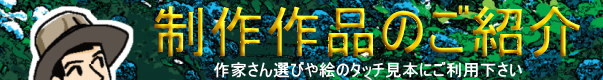 |
�Ƃ�ڃX�^�W�I
��178-0062
�����s���n����1-15-7
�@TEL.03-6760-0230
�@FAX.03-5934-3855
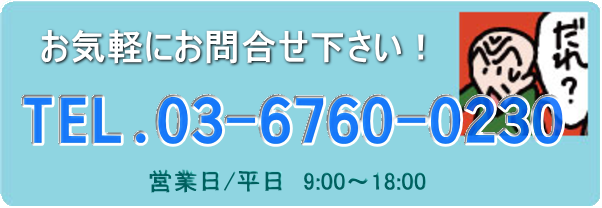
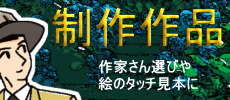
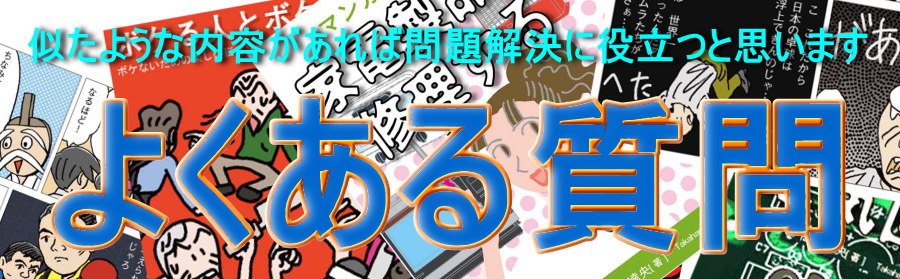


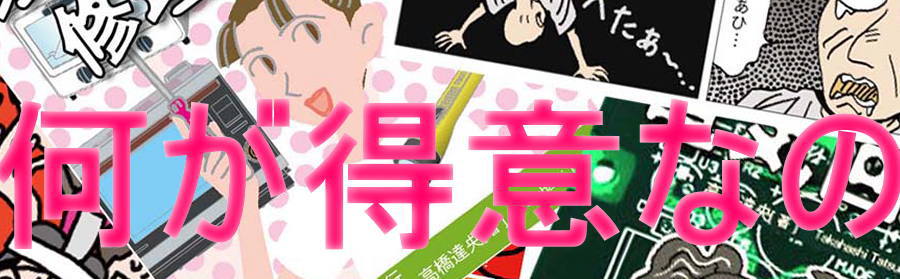

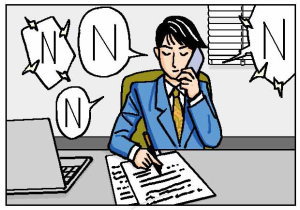 �A�q�A�����O
�A�q�A�����O �C���t����
�C���t���� �E�l���̃y������
�E�l���̃y������ �F�w�i�������
�F�w�i�������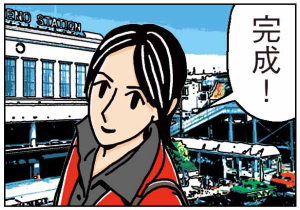 �G����
�G����