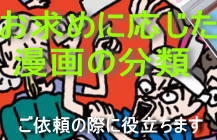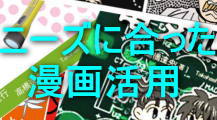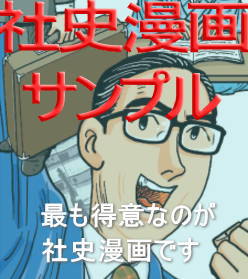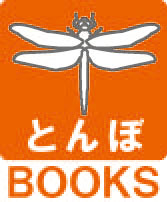「とんぼスタジオ」はプロの漫画家による「漫画」に特化した制作事務所です。
著作権の知識
漫画制作に限らず、写真やデザインなどの著作物を保護する「著作権」という法律があります。著作物を扱うには「著作権」について知っておく必要があります。日本だけに限らず世界中のすべての著作物が「著作権」の対象となり法的に保護されています。ぜひ知っておいて下さい。
| 著作権とは |
| 「著作権」のことを「copyright」ともいいます。世の中には、たくさんの文章や図版や絵画、映像、音楽などがあります。そして、これらすべての著作物には「著作権」があるのです。 こうした著作物を作者に無断で使用すると、著作権の侵害と いうことで司法によって罰せられます。 たとえば、映画やTVの画像を作者に無断でインターネットに投稿していると、これは映画やTV制作者の著作権侵害となります。また、雑誌などに掲載されている写真を無断で転用すると、これも写真家の撮った写真に対する著作権侵害であり、さらに出版権に対する侵害となります。したがって、著作物を自分の作品に転用する際には、必ず著作権者の許可を得なければなりません。許可を得ないで流用または加工することは法律違反になります。 プロの作家さんだけでなく、素人さんの場合にも適用されますのでご注意下さい。ちなみに、インターネットで個人のサイトに使うだけなら著作権侵害にはならない、と考えている方がおられるようですが、これは間違いです。インターネットというのは、個人で楽しむ範疇を越え、不特定多数の人に公開するわけです。したがって、間違いなく違法です。 では、パロディはどうでしょうか? 映画やTVには、他人の作った作品を真似て作った映像があります。これが、いわゆるパロディと呼ばれる作品です。たまにではありますが、漫画にもパロディ作品があります。こうしたパロディは、元の作品を真似たり加工して作っているわけですから、基本的には著作権侵害と考えられます。 ただし、明確な線引きがあるわけではなく、非常に難しい判断となるでしょう。もちろん、著作者の許可を得てパロディ作品を作っているのであれば、なんら問題はありません。しかし、著作者に無断で流用しているのであれば、著作者から訴えられる可能性があるということです。音楽の世界でも、既存の楽曲の一部を流用したということで、著作権侵害として訴訟に発展するケースがあります。 たとえば、プロ野球やJリーグなどのTV中継の映像を、そのまま流用すると放映権の侵害となります。では、自分でプロ野球やJリーグを観戦し、撮影したビデオ映像を流したとします。これはどうでしょうか? この場合は、撮影されている選手の肖像権を侵す行為ということで違法なのです。また、舞踊や演劇を自分で撮影してインターネットで紹介したらどうでしょうか?舞踊や演劇は「肖像権」という扱いですから、作品に対する著作権侵害となります。さらに演じている登場人物の権利を侵害することになります。 次に、「著作権フリー」という明記について述べておきます。よく、素材集や書籍に添付されているCD-ROMなどに、「著作権フリー」と明記されています。単純に考えれば、自由に使って良いと解釈されます。では、著作権も放棄しているのかというと、そうではありません。 著作権は、必ず作者やCD-ROMの制作者が所有しているのです。そして、著作権者は、使用できる範囲や条件を定めてありますから、その範囲を越えて使用すると著作権侵害となってしまいます。 たとえば、「著作権フリー」という明記のそばに、「使用する際には必ず作者の名前をどこかに明記して下さい」とか、「改変は許可しません」といった表記をしてあります。 |
| 著作権保護の具体例 |
| ■制作会社に所属している場合 企業においてプロジェクト制作した著作物については著作者人格権、著作権はすべて制作会社に帰属します。ただし、クライアントに制作物を納品時に、著作権を譲渡することが一般的です。ちなみにサイトの著作権の保護期間はサイト公開後50年です。 ■フリーランスで制作を行う場合 著作者人格権、著作権は著者である作家のものになります。ただしクライアントに制作物を納品する時に、著作権を譲渡することが一般的です。ちなみに、サイトの著作権の保護期間は著作権者の死後50年です。 ■フリーランスで共同制作を行う場合 著作者人格権、著作権は共同制作者のものになります。したがって、複数の共同制作者がいたら、その複数人全員が著作権を有することになります。ちなみにサイトの著作権の保護期間は、最後に死亡した著作者の死後50年です。 |
| Webサイトのレイアウトと配色 |
| 著作権法第2条1には、「著作権」について以下のように述べています。「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、 学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」ちなみにレイアウトは、著作権法における「創作的に表現」したものではなく、「アイディア、手法」の範疇と解釈されます。 つまり、レイアウトは手法ですので、他社のレイアウトを真似しても著作権侵害には抵触しないということです。そして配色についても、他社の配色を真似しても著作権侵害には当たらないということになります。 したがって、レイアウトと配色を模倣して制作しても、著作権で法に触れることはほとんどないということです。ただし、レイアウトと配色が全く同じ場合に、CI(コーポレート・アイデンティティ)から、不正競争防止法で規制される「著名表示の使用行為」とみなされ、法に抵触する可能性があるので気を付けましょう。したがって、あくまでインスパイヤーで留めておく事が必要かと思われます。 |
| ゴッホのひまわりをサイトに使える? |
| 「ひまわり」の制作者ヴィンセント・ヴァン・ホッホは、1890年7月に亡くなっています。したがって、著作権の保護期間が満了していますので自由に改変することができます。当然、サイトのデザインに使用しても、なんら問題はありません。 しかし、たとえ著作物の保護期間が消滅していても、著作物を撮影した写真を利用する場合には注意が必要です。その写真に著作権が発生しますので、今度は撮影者に使用の承諾を得る必要性が発生したりします。 |
| 有名建築物をデザインすることは? |
| 著作権法第46条では、以下のように述べています。「美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」 つまり、都庁やスカイツリーのような有名建築物をデザインに使用したりトレースすることができるということです。ちなみに、「前条第二項に規定する屋外」というのは、「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」のことです。 ようするに、この条文によれば、有名な建築物に限らず、彫刻や絵画でも恒常的に設置される建物や展示物を使用してデザインを行うことができるということです。ただしその建物が販売されている場合や、一時的な屋外のイベント、展示の場合には該当しません。 使用の際には十分に気を付けましょう。 |
| Webサイトの内容を自分のサイトで使用する |
| まず、写真やイラストなどは著作権侵害となります。違法です。 Web上には、著作権フリーの写真やイラストもたくさんありますが、著作権を完全に放棄していない著作物もたくさんあります。使用の際には、Webに明記してあるライセンスや利用規約をよく読んでから利用しましょう。 ただし、たとえ著作権が消滅していない画像などの著作物であっても、引用して利用することができます。その場合の引用の利用原則については、著作権法第32条に明記してあります。 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」 つまり、引用であれば、著作者に承諾を求めなくても利用することができるのです。ただし、絶対ではありません。たとえば以下のような場合には引用が可能であると思われます。 ・明らかに引用したとわかるようにデザインを施す ・報道、批評、研究などではその挿入が必要であることを文書に明記する ・出所や著作名の表示をユーザーにもわかるように明記する このように、画像の著作物に関しては利用についてわかりやすいが、文章に関してはちょっと厄介です。文章については明確な線引きがなく難しいのが現状です。Web上の文章を利用する場合には、あくまで最低限の利用範囲にとどめる必要があります。もちろん、書籍からの引用も同様です。 |
| フォントに関して |
| フォントは、著作権法下では著作物ではないとされています。したがって、フォントを変形させたり切断したりしても、著作権法に 抵触しません。また、フォントをロゴマークとして使用することも、同様に著作権法違反にはなりません。 つまり、文字として読めるロゴデザインは、情報伝達の一部とみなされるからです。ただし、他人がデザインしたロゴを使う場合は要注意です。不正競争防止法の「著名表示の使用行為」にあたる可能性があります。したがって、安易に他人のデザインは真似しないほうが無難です。 しかし、同じ文字であっても「書」など毛筆で制作された作品は「美術の著作物」と認められ、著作権で保護されています。つまり、これらは美術品と同じ扱いであるということです。 |
| ©マークについて |
|
日本では手続きを行わなくても自動的に著作権が発生します。しかし海外では、著作権の発生に手続きが必要な方式主義の国があります。そこで、万国著作権条約(ユネスコ条約)により、以下の3つが表示されていれば、方式主義の国であっても著作権保護が認められています。 ・©マーク ・最初の発行年 ・著作権者名 この3つの表示内容が一致していない場合は表示として不正です。 |
| 参考ページ→ プライバシーポリシー |
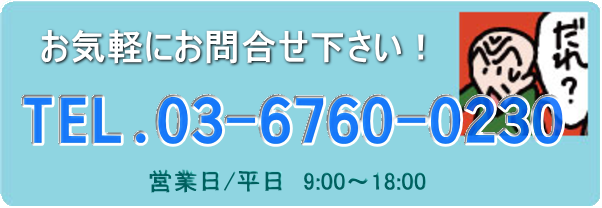
とんぼスタジオ
〒178-0062
東京都練馬区大泉町1-15-7
TEL.03-6760-0230
FAX.03-5934-3855
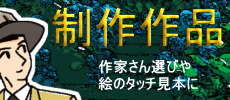
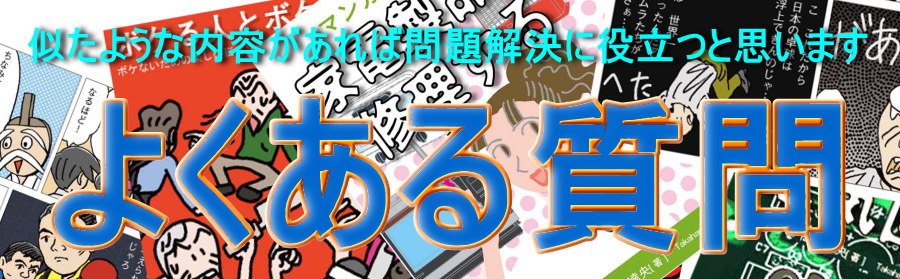


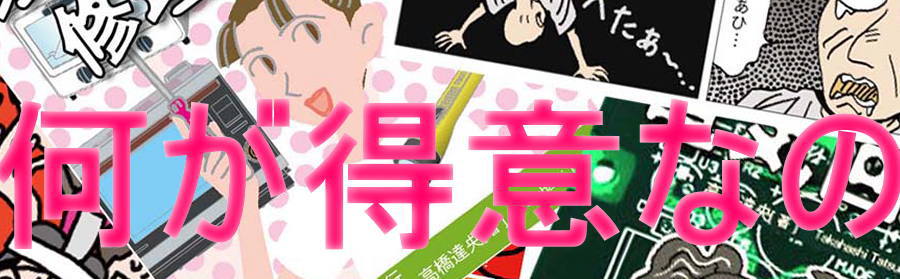

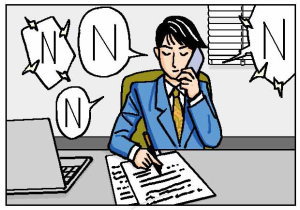 ②ヒアリング
②ヒアリング ④ラフ制作
④ラフ制作 ⑥人物のペン入れ
⑥人物のペン入れ ⑦背景画を入れる
⑦背景画を入れる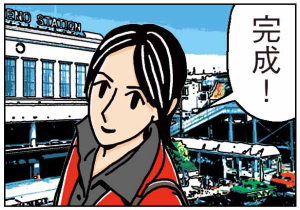 ⑧完成
⑧完成